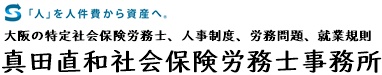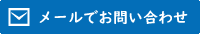同一労働同一賃金の施行5年後見直し
「労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会」において、令和7年2月から同一労働同一賃金の施行5年後見直しについての検討が進められています。
令和7年8月8日に開催された第23回の部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」関係の論点案が示され、その見直しに向けた議論も開始されました。
同一労働同一賃金ガイドラインの見直しについて、今後、この部会で議論していく論点の案は、次のとおりです。
これらの手当の性質や目的を踏まえて、不合理な待遇差がないかが判断されています。
・「正社員人材確保論」については、司法だけでなく現場でも待遇差改善のハードルとなっていることが指摘されており、一時金や退職金の目的に人材確保の目的があったとしても、賃金後払い的性格や功労報償的性格も考慮し、パートや有期契約社員にも割合的な支給や違いに応じた支給が考えられるべきだとされています。
・下級審判決では、褒賞の「業務上特に顕著な功績があった社員に対して褒賞を行う」という要件が形骸化している場合、勤続年数による褒賞とみなされ、正社員と契約社員との間の待遇差が不合理と判断された事例が紹介されています。
・国会答弁や参議院厚生労働委員会の附帯決議においても、労使の合意なき通常の労働者の待遇引下げは、同一労働同一賃金の趣旨に反し、労働条件の不利益変更法理にも抵触する可能性があるとされており、望ましい対応ではないことが示されています。
・「 その他の事情」には、職務の内容や配置の変更範囲に関連する事情だけでなく、職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労働組合との交渉経緯なども含まれることが示されています。
・定年後継続雇用された有期雇用労働者については、その事実のみをもって直ちに待遇差が不合理でないとはならず、総合的な判断が必要であることが示されています。
今回提示された「論点(案)に関する追加資料」では、たとえば、ここ数年の正社員と非正規雇用労働者との間の待遇差が争われた事件の最高裁判決の内容が、退職金、住宅手当、無事故手当、夏期冬期休暇、家族手当(扶養手当)といった待遇の種類ごとに整理して紹介されています。
(厚生労働省 論点(案)に関する追加資料)
令和7年8月8日に開催された第23回の部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」関係の論点案が示され、その見直しに向けた議論も開始されました。
同一労働同一賃金ガイドラインの見直しについて、今後、この部会で議論していく論点の案は、次のとおりです。
1.裁判例を踏まえたガイドラインの見直し
・最高裁判決で示された内容として、退職金、住宅手当、無事故手当、夏期冬期休暇、家族手当(扶養手当)、賞与、病気休職(病気休暇)などが挙げられています。これらの手当の性質や目的を踏まえて、不合理な待遇差がないかが判断されています。
・「正社員人材確保論」については、司法だけでなく現場でも待遇差改善のハードルとなっていることが指摘されており、一時金や退職金の目的に人材確保の目的があったとしても、賃金後払い的性格や功労報償的性格も考慮し、パートや有期契約社員にも割合的な支給や違いに応じた支給が考えられるべきだとされています。
・下級審判決では、褒賞の「業務上特に顕著な功績があった社員に対して褒賞を行う」という要件が形骸化している場合、勤続年数による褒賞とみなされ、正社員と契約社員との間の待遇差が不合理と判断された事例が紹介されています。
2.通常の労働者の待遇引下げによる待遇の相違の解消
・同一労働同一賃金の対応として、正社員の待遇引下げによって対応を図る事例は問題視されており、中小企業でこうした対応の割合が高いことが指摘されています。・国会答弁や参議院厚生労働委員会の附帯決議においても、労使の合意なき通常の労働者の待遇引下げは、同一労働同一賃金の趣旨に反し、労働条件の不利益変更法理にも抵触する可能性があるとされており、望ましい対応ではないことが示されています。
3.「その他の事情」の明確化
・待遇差の不合理性の判断に際して「その他の事情」に「労使交渉」を明示化する提案があり、交渉内容が伴っていることが必要不可欠であるとされています。・「 その他の事情」には、職務の内容や配置の変更範囲に関連する事情だけでなく、職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労働組合との交渉経緯なども含まれることが示されています。
・定年後継続雇用された有期雇用労働者については、その事実のみをもって直ちに待遇差が不合理でないとはならず、総合的な判断が必要であることが示されています。
4.多様な正社員及び無期雇用フルタイム労働者
・定年後再雇用者の雇用形態や所定労働時間、再雇用前後での職務・給与の変化、不満・不安の理由について、調査結果が示されています。特に、職務や働きぶりに賃金・労働条件が見合わない、正社員に比べて賃金や労働条件が低いといった不満が多く挙げられています。5.その他
・パートタイム・有期雇用労働法第8条の趣旨や、労働者からの意見聴取の重要性、賃金決定基準が異なる場合の取扱いに関する注釈などが参照条文や議論として示されています。今回提示された「論点(案)に関する追加資料」では、たとえば、ここ数年の正社員と非正規雇用労働者との間の待遇差が争われた事件の最高裁判決の内容が、退職金、住宅手当、無事故手当、夏期冬期休暇、家族手当(扶養手当)といった待遇の種類ごとに整理して紹介されています。
(厚生労働省 論点(案)に関する追加資料)